水道は私たちの暮らしに欠かせないインフラの一つですが、今、全国的にその料金格差や老朽化問題が深刻化しています。
ある自治体では月額1000円未満なのに対し、他では7000円近い高額負担を強いられている現実があります。
加えて、全国の水道管の多くが耐用年数を超え、漏水や断水のリスクも高まっているのです。
本記事では、そうした問題の全体像と、今後求められる対策について詳しく解説します。
赤穂市が実現する全国最安の水道料金とその仕組み

月額869円という破格の料金が成立する理由
兵庫県赤穂市の水道料金は、全国でも突出して安い月額869円です。これは全国平均の3343円と比べると、4分の1以下という水準です。
赤穂市では生活費を抑えられるという利点があり、移住先や定住地として注目される要因にもなっています。
水道料金の安さは生活の質に直結し、家計の負担を軽減する重要な要素です。
浄水コストの低減と配管距離の短さが鍵
赤穂市の料金がここまで安価である背景には、いくつかの明確な要因があります。
まず、水源が名水百選にも選ばれた「千種川」であり、水質が非常に良好なため、浄水処理にかかるコストが抑えられています。
次に、居住地と浄水場の距離が近く、水道管の総延長が短いため、配管敷設や保守にかかるコストが低く済んでいます。
さらに、江戸時代から水道が整備されていた歴史があり、基盤が古くから構築されていた点も安さを支える要素となっています。
これらの条件が重なり、他地域では実現し得ないような低料金を可能にしています。
全国的に拡大する水道料金格差とその背景

夕張市との料金差は8倍に達している
一方で、全国では水道料金に大きな格差が生まれています。
北海道夕張市では、月額料金が6966円となっており、赤穂市と比較すると約8倍もの開きがあります。
この格差は今後さらに拡大すると予測されており、2046年には最大で20倍を超える可能性があるという報告もあります。
料金差は生活の質や移住の選択にも影響を及ぼし、地域格差を助長する一因となっています。
人口減少が水道事業の採算を圧迫
水道料金の格差拡大には、地域による人口減少が大きく影響しています。
人口が減少すると、使用料が減ることで収益が落ち込みますが、施設維持費はほとんど変わらずにかかり続けます。
兵庫県では、2000年から2040年までに約20%の人口減少が見込まれており、地方を中心に水道事業の運営が困難になりつつあります。
人口減少とともに進む過疎化は、水道だけでなくあらゆるインフラの持続性を脅かしており、抜本的な見直しが求められています。
山間部の配管延長によるコスト増も原因
もうひとつの大きな要因は、地理的な条件です。
山間部などでは、人口が点在しているため、1軒あたりの配管距離が長くなり、敷設・維持コストが高くなる傾向にあります。
道路や鉄道のインフラ同様、水道インフラにも過疎地の宿命ともいえる非効率性が存在しており、それが料金の差を拡大させる一因となっています。
さらに、災害時の復旧コストも高くなりがちであり、自然条件も無視できない影響を及ぼしています。
水道インフラの老朽化が引き起こす具体的なリスク

耐用年数超過の管路が全国の40%に及ぶ
全国の水道管の約40%が、すでに法定耐用年数を超過しています。
耐用年数を超えた設備は、漏水や破損のリスクが大幅に上がります。
更新が行われなければ、水道の安定供給そのものが脅かされることになります。
老朽化によってインフラ全体がリスク要因となり、地域の安全性にも直結する課題です。
水質悪化や漏水事故のリスクが増大
老朽化した水道管では、内部のサビや腐食が進み、水質が悪化するリスクがあります。
また、管の破裂や漏水も起こりやすくなり、2021年には和歌山市で大規模な断水事故が発生しました。
このような事例は、全国の他の自治体でも決して例外ではありません。
特に漏水が多い地域では、水が無駄に流れ出し、使用されることなく失われる「無収水率」が30%を超えるケースも確認されています。
これは利用者の水道料金に跳ね返る形で、さらなるコスト増を引き起こします。
財政破綻の危機に直面する水道事業とその実情
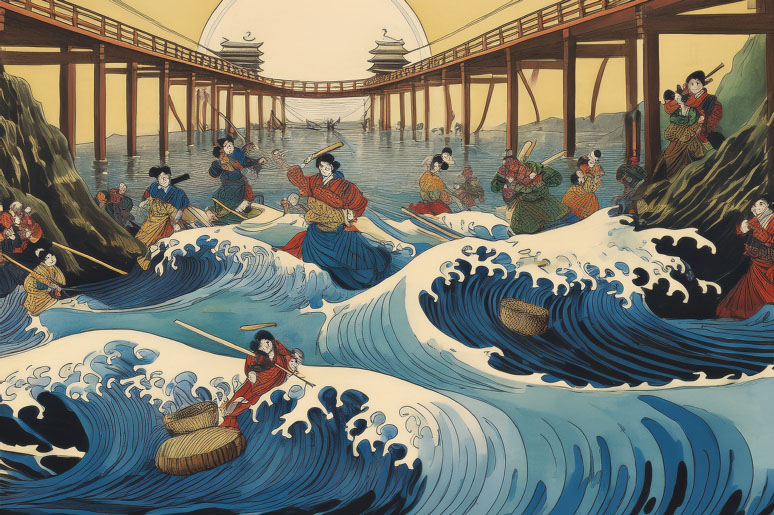
維持費高騰と職員減少が追い打ちをかける
水道料金が安く抑えられている地域ほど、将来的な更新費用の負担が大きくのしかかります。
加えて、人口減少による料金収入の減少に加え、水道関連職員の減少も進んでいます。
兵庫県では、過去10年間で水道部門の職員数が約15%減少しており、人材不足による運営体制の弱体化が懸念されています。
専門知識が求められる分野での人材減少は、インフラ更新計画やトラブル対応の遅れを生み、さらなるリスクを招いています。
年間2兆円規模の更新費が必要とされる
専門家の試算によれば、全国の水道インフラを今後も安全に維持するには、年間で約2兆円の投資が必要とされています。
しかし現在の更新ペースでは資金が追いつかず、「10年以内に現金が尽きる自治体が続出する」との警告もあります。
このままでは持続可能な水道運営が難しくなる自治体が増えていくでしょう。
財政面での持続性を担保するには、収支のバランスだけでなく、将来的な人口動態までを見据えた中長期計画が不可欠です。
広域化や民間連携などの対策が模索される現状

自治体間の連携による効率化を模索
水道事業の広域化は、現在進められている主な対策のひとつです。
複数の自治体が連携し、水源や浄水場を共有することで、設備投資や人員配置の最適化を図ることができます。
実際に、兵庫県内でも41の事業体が存在しており、統合によるコスト圧縮が検討されています。
自治体の垣根を越えた連携が、水道の未来を支える可能性を秘めています。
民間資金の活用と制度改革の必要性
もうひとつの有力な選択肢は、民間資金を活用することです。官民連携によって運営効率を高め、財政的な持続性を確保する動きも始まっています。
ただし、民間委託にはサービス低下や情報の不透明化への懸念もあり、制度設計には慎重な議論が必要です。
信頼性の高い仕組みと透明性を担保するためのルール整備が不可欠です。
将来に備えた利用者意識と政策の再構築が不可欠

利用者にも求められる理解と協力
水道料金の値上げは利用者にとって負担ではありますが、インフラの安全性と継続性を確保するには避けて通れない現実です。
行政だけに任せるのではなく、私たち一人ひとりが必要なコストとして理解し、協力する姿勢が求められます。
持続可能な水道を維持するために、節水意識や老朽化対策に関心を持つことも大切です。
中長期的な視点での改革が必要
単なる対症療法ではなく、水道制度を築くには中長期的な視野が必要です。
国の補助金だけでなく、地域ごとの事情に応じた柔軟な運用と制度設計が不可欠です。
民間のノウハウと公共の責任を両立させる、新たな公共サービスの形が求められています。
技術革新やデジタル管理の導入も、今後の制度改革において鍵となる要素です。
まとめ
- 赤穂市は全国で最も安い水道料金を維持しています。
- 浄水コストの低さと配管距離の短さが低料金の要因です。
- 地域間で最大8倍、将来的には20倍の格差が予測されています。
- 水道管の老朽化は漏水や断水など深刻な問題を引き起こします。
- 財政難により、維持費用が確保できない自治体が増えています。
- 広域連携と民間活用は、水道運営の効率化と安定化に役立ちます。













